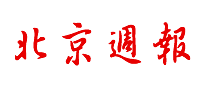|

1958年初秋のある日の正午。ラサの北郊外にあるラル湿地の北端、セラウズ山の南麓の大通りの両側で、石を境界(警戒線に相当)とし、1本の「神道」が形づくられた。威風堂々とした厳かな隊列がゆっくりとこの荒れ果てた神聖な土の道を行進し、彼らは黄色の絹織物で包まれている大きなかごを取り囲んでいる。かごの前にクジャクの傘をかかげる人がおり、かごの上方にひっきりなしにぐるぐる回るとばりのような絹のかさが広げられている。この大きなかごと2つの聖なる傘はすべて清朝の皇帝から下賜されたもので、生まれ変わった歴代の活仏が出かける際の専用する神聖なものである。西暦1652年、5世ダライラマが上京して清朝の皇帝にまみえた時、順治皇帝がダライラマに金の天頂のついた黄色のかごを贈り、国の都に入らせた。北京を離れる時に黄色のかごをたずさえてチベットに戻らせた。その時から、ダライラマが出かけるたびに必ず皇帝から下賜された黄色のかごに乗ることになっていた。その後の歴代のダライラマはこの儀仗の規則を踏襲し、一般はいずれもかごに乗って出かけることになっていた。
蘇州・杭州産の絹織物で縫製した官服をまとい、大きくて高い馬に乗っている貴族と僧侶ら。古い制度に従って、僧侶官吏は前に、非僧侶官吏は後ろにおり、各クラスの官吏は職位と官階の高低によって、威風堂々として順次前進する。歩行する者の多くは農奴あるいは奴僕であったが、その装備が整然としており、服装も鮮明で、彼らは護衛兵あるいは侍従で、途中で主人のために馬を引き、鐙をつけ、あらゆる手を尽くして自分の主人を護衛し、世話をしていた。16人の「清兵」(清王朝の兵士)の身なりのかご担ぎは穏健で調和のとれた足並みで皇帝から下賜されたかごを小心翼翼として担いでいた。かごの中に黙々として坐っているのは人々の上に立つ若くて孤独な活仏であり、彼は好むかどうかに関わらず、必ず背くことのできないわだちに沿って、ゆっくりと進まなければならない。
当時、普通の庶民はすべて「神道」をまたがり越えることは厳禁とされ、警戒線の外で拝謁、観覧あるいは通行することだけが許されていた。(写真・陳宗烈)
|